
|
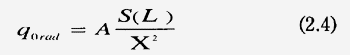
Aは定数、S(L)(m 2)は火炎放射面積、X(m)は火炎中心までの距離とする。実験によれば火炎の中心から火源寸法の約3倍以上離れた場合、逆2乗則が成立する。
図2.2.4は実験データと推定値を熱放射強度と無次元距離で整理したデータである。推定値の熱放射強度は形態係数と放射熱発散度の積として次式で与えられている 5)。
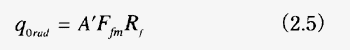
ここで、A’は定数、Fは形態係数、Rf(Wm −2)は次式の放射熱発散度を表す。放射熱発散度は発熱体の温度や後述の吸収の影響を含んだものと考えることができ次式で与えられる。
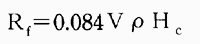
ここで、Vは燃焼速度(mh−1)、ρは液密度(kgm−3)、Hcは燃焼熱(Jkg −1)を表す。形態係数は、火炎を円筒と見なしたとき、受熱体の微小平面が円筒の底面と同一面にあるとして次式で与えられる。
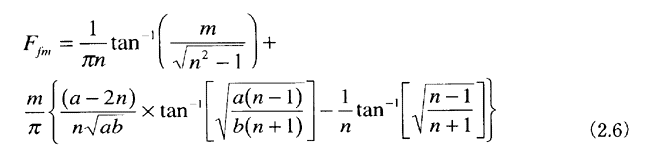
ここで
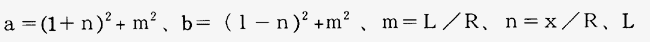
は火炎長、Rは円筒の半径、xは円筒の中心までの距離である。
実験結果はタンク径が大きくなると推定値よりかなりはずれることを示しており、このような大規模な火炎については未解明な点が多い。
[吸収長]
放射熱は火炎の周りに発生する煤や蒸気によって吸収され、その程度は吸収層の厚さや吸収係数によって決まる。吸収層を通過した放射熱はランバートベール
前ページ 目次へ 次ページ
|

|